今年の干支|2025年【令和7年】

巳年(みどし)
乙巳(かのとみ)
巳年の年齢(現在)
誕生日の前であれば-1歳で計算してください
| 西暦・和暦 | 干支 | 満年齢 |
|---|---|---|
| 2013年 平成25年 | 癸巳 みずのと・へび | 11歳 |
| 2001年 平成13年 | 辛巳 かのと・へび | 23歳 |
| 1989年 平成1年 | 己巳 つちのと・へび | 35歳 |
| 1977年 昭和52年 | 丁巳 ひのと・へび | 47歳 |
| 1965年 昭和40年 | 乙巳 きのと・へび | 59歳 |
| 1953年 昭和28年 | 癸巳 みずのと・へび | 71歳 |
| 1941年 昭和16年 | 辛巳 かのと・へび | 83歳 |
| 1929年 昭和4年 | 己巳 つちのと・へび | 95歳 |
| 1917年 大正6年 | 丁巳 ひのと・へび | 107歳 |
| 1905年 明治38年 | 乙巳 きのと・へび | 119歳 |
巳年の性格と相性
プライドが高いのが特徴ですが、上手にコミュニケーションをとればしっかりと結果を出してくれる性格です。
冷たい性格に見えますが、とても知的で場を和ませるタイプなので、付き合いが長くなると面白さにも気づけます。
巳年との相性
| 相性 | ポイント | |
|---|---|---|
| ねずみ (子) |
△ | 些細な隠し事、嫉妬心でいざこざ |
| うし (丑) |
◎ | 良いパートナーになれます |
| とら (寅) |
△ | 時間が長くなるほど イライラが募ってしまいます |
| うさぎ (卯) |
○ | 衝突することはありません |
| たつ (辰) |
〇 | 良い関係になれます |
| へび (巳) |
△ | 優れたチームワークになりますが 対立することも |
| うま (午) |
○ | 刺激しあえる関係 |
| ひつじ (未) |
△ | 相容れない関係になりやすい |
| さる (申) |
○ | 上に立つかで争うことも 良きライバルになれば○ |
| とり (酉) |
◎ | 素晴らしい結果を出せる関係 |
| いぬ (戌) |
△ | 心を開くのに時間がかかりそう |
| いのしし (亥) |
〇 | 何かにつけて正反対 |
来年の干支|2026年(令和8年)

午年(うまどし)
丙午(ひのえうま)

「今年の干支は何?干支とは?数々のギモンを徹底調査!」
「今年の干支は何だっけ?」
「来年の干支は?」
年賀状の季節になると、そのような干支の話題が出ることはありませんか?
今年2025年【令和7年】の干支は、卯年です。うさぎですね。
ちなみに、来年の干支|2026年【令和8年】は、辰年です。
実は、干支=十二支ではないということはご存じでしょうか?
正確にいうと、2023年の干支は、癸卯(みずのとう)なんです。
この記事では、そんな知っているようで知らない干支について、徹底的に調べました。
ぜひご覧くださいね。
干支とは
それではまず、干支の基本的なところをご説明します。
ポイントは、
・干支の読み方
・干支が表すもの
この2つです。
ひとつずつ紹介していきますね。
干支の読み方は2つある
あなたは「干支」って、どのように読みますか?
実は、「えと」「かんし」2通りの読み方があるんです。
「どちらが正解なの?」
と思う人もいるでしょう。実は、どちらでもOKです。
干支を正確にいうと、「十干十二支(じっかんじゅうにし」。「干」「支」という言葉が入っているのがわかりますか? ここから「干支」という言葉が生まれました。
ラベル 干支の読み方|音読みと訓読みまとめてみたよ十干十二支が表すもの
十干は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸です。
十二支は、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥ですね。
この十干十二支、干支の組み合わせは、60通りになります。
干支のはじまりは甲子(きのえ・ね)。60番目が癸亥(みずのと・い)です。
2019年の干支の己亥(つちのと・い)は、36番目です。そこから、2020年庚子(かのえ・ね)、2021年辛丑(かのと・うし)と続いていきます。
これを使って、年月日や方角、時刻なども表していました。年も時間もすべて一周巡るものという考えだったのですね。
古来中国では、最も尊い星が木星だとされていました。その木星が約12年で一周することから、年は12年で一周することになったというわけです。
よく60歳になると還暦祝いをしますよね。これは、干支が一周まわって還ってきたということのお祝いです。昔は60歳まで生きることが難しかったため、盛大に祝うようになったといわれています。
干支が気になること同じように気になるのが今年の厄年!ではありませんか?
▶ 厄年がわかる
▶ 2020年の男性の厄年
▶ 2020年の女性の厄年
| 2020年(令和2年)の年祝い | ||||
| 還暦 かんれき 61歳 | 緑寿 ろくじゅ 66歳 | 古希 こき 70歳 | 喜寿 きじゅ 77歳 | 傘寿 さんじゅ 80歳 |
| 半寿 はんじゅ 81歳 | 米寿 べいじゅ 88歳 | 卒寿 そつじゅ 90歳 | 白寿 はくじゅ 99歳 | 百寿 ももじゅ ひゃくじゅ 100歳 |
干支のひとつ・十二支の謎
十二支は、ねずみ・うし・とら・うさぎ・たつ・へび・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・いのししです。
この十二支にまつわる疑問やエピソードをまとめてみました。
- なぜ普段使われている漢字と違うのか?
- なぜ動物が当てはめられたのか?
- 十二支が決まったエピソード
- 十二支に入れなかったネコの話
- 十二支に入れなかったイタチの話
- 十二支ごとの性格や特徴
ひとつずつご説明します。
なぜ普段使われている漢字と違うの?
十二支は、子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥です。普段使う漢字とは、ちがいますよね。
日本では、見慣れない漢字もありますが、実は中国では使われている漢字です。中国の漢字をそのまま使っているというわけですね。
なぜ動物が当てはめられたの?
次に、なぜ動物があてはめられたのかという疑問です。
そもそも十二支は、年月日や時刻を表すための記号でした。その記号を覚えやすくするために、動物をあてはめたといわれています。
ちなみに、亥は中国では豚です。他の国の十二支も、一部ちがう動物があてはめられています。
そして、ただ動物を適当にあてはめたのではありません。ちゃんとそれぞれ意味があります。
ねずみ
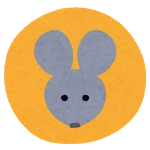 ねずみは、子孫繁栄という意味があります。
ねずみは、子孫繁栄という意味があります。
ねずみは子どもをたくさん産み、成長も早いことからあてはめられました。「財」の意味もあります。
うし
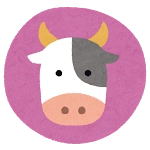 牛は、堅実さと粘り強さという意味です。
牛は、堅実さと粘り強さという意味です。
牛は、労働力としても、大切な食料としても重要な存在です。ゆっくりながらも確実に進んでいくことからあてはめられました。
とら
 虎は、決断力と才知。
虎は、決断力と才知。
虎は、その動きの素早さから、頭のはたらきが素晴らしいといわれ、才知(才能と知恵)の象徴とされています。また、毛皮の模様が美しいことから、虎は前世は輝く星であったと考えられ、ものごとの始まりの象徴ともいわれています。
うさぎ
 うさぎは、家内安全と飛躍という意味があります。
うさぎは、家内安全と飛躍という意味があります。
うさぎの温厚おだやかな様子から、家内安全の象徴とされています。また、ぴょんぴょん飛び跳ねる姿から、飛躍を意味しています。
たつ
 たつは、正義や信用という意味です。
たつは、正義や信用という意味です。
架空の生き物である龍は、伝説の存在であることから吉兆をもたらすといわれ、権力者の象徴とされました。
へび
 へびをあてはめた意味は、豊穣と情熱。
へびをあてはめた意味は、豊穣と情熱。
へびは、お金に縁の深い生き物とされています。また、へびは執念深いといわれていますが、助けてもらった恩はきちんと返すともいわれます。脱皮を繰り返すことから、生命力の象徴ともされていますね。
うま
 馬は、豊作と健康という意味があります。
馬は、豊作と健康という意味があります。
昔から人との関わりがある馬は、牛同様とても役立つ存在です。
ひつじ
 羊は、安泰です。
羊は、安泰です。
羊は群れをなしていることから、家族安泰の象徴とされ、いつまでも平和に暮らせるということを意味しています。
さる
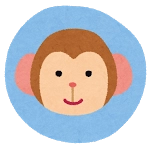 猿をあてはめた意味は、知性や臨機応変さです。
猿をあてはめた意味は、知性や臨機応変さです。
猿は山の賢者といわれ、知性の象徴とされています。昔から山神の使いだともいわれ、信仰されています。
とり
 鳥は、親切という意味があります。
鳥は、親切という意味があります。
鳥は、人に時間を教えてくれるということで、大切にされてきました。
いぬ
 犬をあてはめた意味は、勤勉や忠実。
犬をあてはめた意味は、勤勉や忠実。
犬は、人にとても忠実であることで知られています。また、社会性もあるといわれています。
いのしし
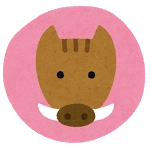 猪は、無病息災という意味です。
猪は、無病息災という意味です。
猪は田や作物の神といわれています。また、肉が万病を防ぐともいわれていたことから、無病息災の象徴とされています。
十二支が決まったエピソード
これまで書いてきたように、漢字が記号として先にあり、そこに動物をあてはめていったので、動物の順番に意味はありません。
しかし、十二支にまつわる有名な言い伝えがあるのをご存じでしょうか?
この言い伝えは、地域などによって違う点があります。
でも、
・たどり着いた順であること
・ねずみは牛に乗って行き、着く直前に飛び降り、1番になった
という点は、共通しています。
ここでは、中国に伝わる言い伝えをご紹介します。
十二支を決める動物たちの競争
中国道教の最高神とされる玉皇大帝(以下、皇帝)は、ある日動物たちに会議を開くから集まるよう言いました。
そして、12ある年に名前を付けたい、会議に到着した順に、その動物の名前を付けると動物たちに言ったのでした。
動物たちは、皇帝いる宮殿に向かいましたが、その道中には大きな川がありました。その川を越えなくては、たどり着くことができません。
しかし、ねずみは泳ぐことができませんでした。そこで考えたのが、牛の背中に乗せてもらうことでした。
ねずみは、道案内をするからと言って、牛の背中に乗せてもらい川を渡りました。ねずみは、対岸に着くと、牛から降りて一目散に宮殿へ。それで、ねずみが1番になりました。
牛がその後に続いて2番。
3番目は虎です。虎は川を力強く泳いで渡りました。
4番目のうさぎは、ぴょんぴょん跳ねながら、川の小石づたいに川を渡っていました。途中立ち往生してしまったうさぎは、丸太に飛び移ります。そのまま流されてしまったうさぎでしたが、5番目に来た龍に助けられ、無事到着しました。
その次は、馬です。馬は龍の次に宮殿に到着しました。ところが、馬のひづめにへびが隠れていたのです。
急に足元からへびが出てきて、馬はびっくりして、後ろに下がりました。そのすきにへびは宮殿へ入ったので、へびが6番。馬が7番目になりました。
続いてやってきたのは、羊を猿と鳥でした。3匹は、協力し合って川を渡り、宮殿に到着しました。
11番目は犬でした。犬は動物たちの中でも泳ぎが得意です。しかし、ついつい水遊びをしてしまって遅くなってしまいました。
最後、12番目は豚です。途中でおなかがすいて、ご飯を食べていたら遅くなってしまいました。
以上が、十二支にまつわる言い伝えです。
日本では、12番目は猪です。そのため日本で伝わるお話は「猪はまっすぐしか走れず、宮殿を通り過ぎてしまった」というお話が多いですね。
さて、十二支に入ることができた動物たちのお話をしてきましたが、入ることができなかった動物もいます。
その中でも有名な、ネコとイタチの話もご紹介します。
十二支に入れなかったネコの話
ネコは、十二支に入ることができませんでした。この理由にも所説ありますが、共通しているのは「ねずみのせい」だということです。
有名なお話は、「ねずみがネコにウソを教えた」というもの。
ネコがねずみに「宮殿に行くのはいつか」と聞いたところ、ねずみは間違った日を教えました。それで、ネコは十二支に入れなかったのです。ねずみがネコをだましたんですね。
他にも、ネコは最初ねずみと牛の背中に乗っていたというお話もあります。川を渡っているときに、ねずみはネコを川へ突き落としました。ネコは泳げず流されてしまい、宮殿には行けなかったのです。
そのため、ネコがねずみを追いかけるようになったのは、この十二支に入るための競争が原因だとされています。
十二支に入れなかったイタチの話
もうひとつ有名なのが、イタチの話です。
イタチには、皇帝が動物たちに集まるように言ったという知らせが届いていませんでした。イタチは十二支の話を後から聞くと、皇帝のところへ行き、なんとか十二支に入れてもらえないかと訴えました。
知らせが届いていなかったということを気の毒に思った皇帝は、月の最初の日をイタチの日とすることに決めました。
しかし、他にも十二支に入れなかった動物がいる手前、頭に「つ」を付けて、「ついたち」と言うことにしたのです。
月の最初の日「1日」を「ついたち」と読むのは、この話が由来だといわれています。
干支(十二支)ごとに見る性格の違い
さて、この十二支ですが、十二支ごとに性格の特徴があるといわれていることをご存知ですか? あなたも自分の十二支を確認して、当たっているかどうか確認してみてください。
ねずみ
ねずみ年の人は、どこででも生きていけるたくましさと適応能力があります。用心深いところがあり、細かなところも気づきます。コツコツ努力することができ、大器晩成型といえるでしょう。お金の使い方に注意が必要です。
うし
うし年の人は、マイペース。根気よく物事に取り組めるので、信用も得られやすいです。基本的に穏やかで優しい性格ですが、怒ると止まらなくなる傾向があります。
とら
とら年の人は、チャレンジ精神旺盛で、いろんなことに興味を持ち、積極的に行動します。リーダー的存在になることが多いですが、独立心も強いので、単独行動のほうがうまくいきやすい傾向があります。頑固なところがあるので、特に目上の人とトラブルになりがちなので注意しましょう。
うさぎ
うさぎ年の人は、お人好しな性格。人当たりが良いので、小さい頃から人気を得られやすい傾向があります。気分屋なところがあり、傷つきやすい性格の持ち主が多いです。
たつ
たつ年の人は、あまり表には出しませんが、高い理想を内に秘めています。直観力や実行力も兼ね備え、個性的な性格であるといえます。プライドが高く、負けず嫌いなところがあります。
へび
へび年の人は、物事を深く考えることが多く、粘り強さがあります。また、世話好きな一面もあります。思い込みが激しいところがあるので、注意しましょう。
うま
うま年の人は、頭の回転が早く、要領がいいので、人間関係がうまくいきます。人付き合いは広く浅くという人が多いです。穏やかでありつつも、いざというときの行動力があります。細かいことが苦手な傾向があります。
ひつじ
ひつじ年の人は、家族や友人など周りの人たちを大切にします。その反面、周りの人たちに気を使いすぎるところもあるので、無理せず息抜きする時間も大切にしましょう。
さる
さる年の人は、器用で頭の回転が早い人が多いです。世渡り上手といえるでしょう。じっとしていることよりも、動き回っているほうが合っています。しかし、飽きやすい一面もあるので、特に人間関係においては注意が必要です。
とり
とり年の人は、勘がするどく、誠実な人が多いです。自由を求め、さっぱりした性格なので、人間関係もうまくいく傾向があります。その反面、内心を明かしたがらない一面もあります。
いぬ
いぬ年の人は、正義感にあふれる真面目な人が多いです。保守的でもあるので、決められたルールをきちんと守ろうとします。頑固な面もあるので、人から干渉されるのが苦手だと感じるでしょう。
いのしし
いのしし年の人は、誠実で義理堅い性格です。一途なので、相性の良い人に出会えれば、その人をずっと大切にします。せっかちな面がある一方で、我慢強い人も多い傾向です。個性的でわかりにくい性格なので、他人から誤解されがちです。
干支のひとつ・十干とは
次は、干支のひとつ、十干についてわかりやすくご説明します。十干は、十二支ほどなじみがないかもしれませんね。
十干は10種類
十干は、10種類あります。読み方も合わせて紹介すると、甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(
き)です。これは、主に順番を表すときに使います。
この十干で日付を表すときには、また読み方が変わってきます。
甲(きのえ)・乙(きのと)
丙(ひのえ)・丁(ひのと)
戊(つちのえ)・己(つちのと)
庚(かのえ)・辛(かのと)
壬(みずのえ)・癸(みずのと)
こうして見てくると、十干の読み方に法則があるのがわかります。実はこれは、十干が五行陰陽説と深い関係があることに由来しています。
十干と五行陰陽説との関係
まずは、五行説と陰陽説に分けて説明していきます。
五行説とは、中国に由来する思想です。「万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなる」という考え方です。
陰陽説は、「万物は、すべて陰と陽の2つのエネルギーによって構成されている」という考え方です。
日本では、この五行陰陽説を十干にあてはめました。日本では、「陽」を「兄(え)」、「陰」を「弟(と)」と呼ぶようになりました。「干支」を「えと」と読むのは、このことが由来になっています。
例えば「甲」は、五行説では「木」陰陽説では「兄」があてはめられ、「きのえ」となったのです。
身近にある十干
普段の生活には、あまりなじみのなさそうな十干ですが、実は身近でも使われています。昔から数字や順番を表すのに使われていた名残が、いまもあります。
「甲乙つけがたい」という言葉を聞いたことはありませんか? これは、2つのものに差がなく、どちらが優れているのか判断が難しいという意味です。
甲と乙。つまり、1番と2番が決められないという意味なんですね。
他にも、アルコールの種類や資格で、甲種乙種というものがあります。また、契約書でも甲乙が使われていますね。
さらに、十干は日付を表していますが、10日で一巡します。これを、昔は「一旬」と言っていました。1ヶ月はこれを3回くり返すことになります。ここから、上旬・中旬・下旬という言葉が生まれました。
身近にある干支
干支も身近で使われています。「実は干支が由来だった!」というものが、たくさんあるんですよ。。
時間の表現
時間の表現で、「午前」「午後」をよく使いますよね。これは、午の刻が午後0時というところからきています。午の刻の前か後かということなんですね。
また、時間を表すときは、子の刻を午前0時(午後11時~午前1時)として、12分割して十二支をあてはめていました。
幽霊が出そうな不気味な時間として、「丑三つ時」というのを聞いたことはありませんか?
丑の刻は午前1時~3時にあたります。
昔はここから、さらに4分割30分ごとに分けていました。つまり、「丑三つ時」は、午前2時~2時30分頃を指しています。たしかに夜も更けた幽霊が出そうな時間ですよね。
方角
次に方角です。方角で干支を意識するのは、恵方巻きを食べるときぐらいかもしれません。すっかり節分のイベントとして定着していますよね。
この恵方巻きを恵方(吉方)に向けて食べると良いことがあるといわれています。恵方に向かって黙って1本食べ切ると良いという話は有名です。
恵方に何があるのかというと、年神様がいる方角を指しているのですね。そのため、恵方巻きを食べるときだけでなく、初詣や大事なことをおこなうときは、その年の恵方を意識することもあります。
そして、年神様は、毎年移動します。その方角を示しているのが、干支なのです。
基本的に方角は、子が北で、時計回りに12分割します。しかし、恵方を調べるときは、十干も使われます。さらに艮(うしとら)・巽(たつみ)・坤(ひつじさる)・乾(いぬい)の4つも加わります。つまり、合計26で方角を示しているということになります。
歴史や名前の由来になっている
歴史上のできごとは、そのできごとがあった年の干支を使って名付けられたものがあります。
例えば、戊辰戦争です。これは、1868年(明治元年)から始まりました。この年の干支が戊辰(つちのえ・たつ)だったことが由来です。
壬申の乱も同様で、672年(天武天皇元年)から起こったものなので、その年の干支、壬申(みずのえ・さる)が由来となっています。
また、ネーミングが干支に由来しているものがあります。有名なのが、甲子園球場ですね。甲子園球場が完成したのが、1924年(大正13年)。この年の干支が、甲子(きのえ・ね)だったことから、甲子園球場と名付けられました。
甲子は、干支の1番目にあたります。大変縁起が良いということで、この甲子園球場一帯の地名も「甲子園」になりました。
カレンダーを見てみよう
干支は、カレンダーに書いてあることもあります。年だけでなく、月や日ごとにも干支が決まっているのです。それぞれ、年干支・月干支・日干支と呼ばれています。
共通しているのが、「60の干支が循環している」ということです。そこには、元号は関係ありません。改元したとしても、干支は循環し続けます。
そのため、干支を調べれば、「このできごとは〇年前に起きた」ということがわかるようになっています。残念ながら、干支がいつから始まったかという詳細な記録はありません。しかし、その年の干支を見れば、今から何年前に起きたことなのかの判断ができるのです。
頻繁に改元されていた時期もありますので、干支の記録が残っているとわかりやすいですね。
まとめ
干支、十干十二支の歴史や言い伝え、性格などをまとめました。
これからは「十二支」だけでなく、「干支」を意識してみてはいかがでしょうか。
